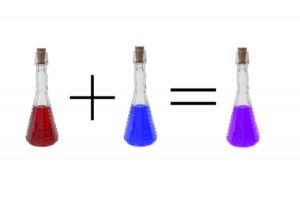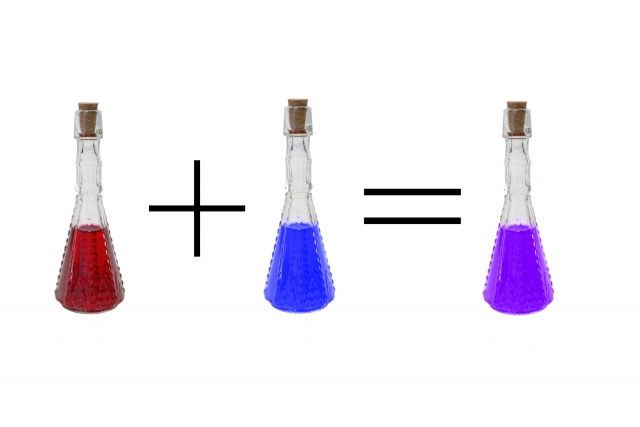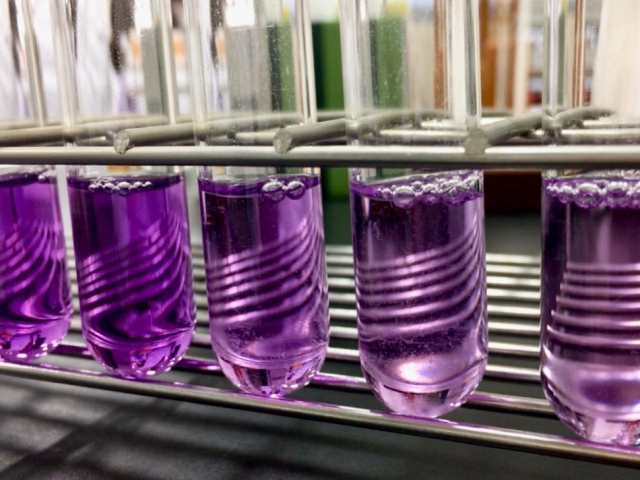反応速度
化学反応とは、反応物の結合が切れ、原子間に新しい結合が形成し、生成物が生じることです。化学反応では、生成物をつくるときに、結合を1度切らなければならないので、結合エネルギーの大きい分子などは、化学反応が起こりにくくなります。新しい結合ができる際にも、分子の構造が複雑に絡み合っていると、立体的な障害のため、生成物が生成しにくいこともあります。したがって、化学反応は、すぐに終わることはなく、反応物にエネルギーを与えて、結合の切断や再結合しなければならず、ある程度の時間がかかります。
化学反応式における1つの物質に注目したとき、単位時間あたりのモル濃度の変化量をその物質の反応速度(reaction velocity)といいます。モル濃度を使う理由は、反応速度は体積の影響を受けるからです。大きい容器と小さい容器があれば、当然小さい容器の方が激しく反応が起こります。したがって、反応速度は、体積の影響を考えたモル濃度を使って表します。
反応速度を支配する要因
化学反応を進行させるためには、化学結合を切るだけのエネルギーが必要になります。反応を進行させるためには、まずは反応物の粒子同士が衝突しなければなりません。しかし、反応物同士が衝突したからといって、必ず反応するとは限りません。多くの化学反応では、反応が起こるためには、ある一定以上のエネルギーを加えて、化学結合が切れやすい活性化状態にしなければなりません。加える最小のエネルギーを、一般的に活性化エネルギー(activation energy)といいます。活性化エネルギー以上の運動エネルギーを持たない粒子同士の衝突では、反応は進行しません。
したがって、反応物に活性化エネルギー以上のエネルギーを与え、反応速度を大きくするためには、一般的に以下が必要となります。
反応物の濃度を大きくする
化学反応を進行させるためには、反応物同士の衝突が必要不可欠です。一般的に単位時間当たりに衝突する反応物の数が多いほど、反応速度は大きくなります。反応物が移動しやすい気体や溶液中の反応では、反応物の濃度を大きくすると、反応物同士が衝突する確率が大きくなるので、反応速度は大きくなります。
固体が関係する反応では、固体を細かくしていくと反応速度は大きくなります。これは、同質量では、塊状より粉末状の方が、表面積が著しく大きくて、互いに接触できる粒子の数が、極めて大きくなるためです。
温度を上げる
温度を上げると、高い運動エネルギーを持つ割合が増加します。そのため、反応物同士が衝突したときに、活性化エネルギー以上の運動エネルギーを持った粒子の割合が増加します。温度が高くなると、活性化エネルギー以上のエネルギーを持つ反応物の数が、急激に増加します。多くの化学反応において、室温付近では温度が10 ℃上がるごとに、反応速度はおよそ2倍になります。
触媒を加える
反応の前後でそれ自身は変化しないものの、反応速度を大きくするような物質を、触媒といいます。触媒は、反応物との間で、反応中間体をつくります。反応中間体から生成物ができるとともに、触媒が再生されます。触媒を加えると、反応の仕組みが変わって、活性化エネルギーが小さくなるため、活性化エネルギー以上の運動エネルギーを持つ分子の割合が増加します。触媒は、新たな活性化状態を作って、活性化エネルギーを小さくし、反応速度を大きくする効果があります。ただし、触媒は活性化エネルギーを小さくしますが、反応熱は変化させません。また、触媒は逆反応の活性化エネルギーも小さくするので、逆反応の反応速度も大きくなります。体内や食品産業で使用する酵素も触媒です。
実際の反応は、より複雑である場合が多く、いくつかの反応が組み合わさって進みます。
アレニウスの式と賞味期限の設定
スウェーデンの科学者アレニウスが提唱したアレニウスの式は、ある温度での化学反応の速度を予測する式です。反応速度は、10℃上がる毎に2倍になります。
食品の賞味期限を設定するために、日本缶詰協会が設定する賞味期限策定根拠のひとつであるアレニウスの式に基づいた加熱加速度(虐待)試験を実施します。日本では、20℃を基準温度として、30℃で2倍、40℃で4倍、50℃で8倍の加速度で物質の反応が進むと考えて試験を行います。
食品の品質劣化は、温度や湿度、光、酸素などの影響を受け進行します。アレニウスの式に基づいて加熱加速度試験を実施し、食品の賞味期限を確認するために、油脂の酸化度や変質の程度を判定する酸価(AV)や過酸化物価(POV)、食品のアルカリ性や中性、酸性の程度を測定するpH値、味やにおい、外観を評価する官能検査、菌検査を行い、食品として可食か否かを判定します。
具体的には、非常食などの該当する食品を50℃の恒温槽などで保管します。半年間182.5日保管した場合、アレニウスの式により8倍相当の期間である1,460日となります。ここに安全係数0.7をかけ、1,022日となります。官能検査などをもとに問題なければ、この日数を賞味期限として、設定します。
温度を上げることによる食品への影響
多くの食品は、加熱処理により提供されます。この加熱工程において、食品中のたんぱく質の変性や食品原材料からの成分の溶出、メイラード反応をはじめとする化学反応など多くの反応が起こり、食品の呈味が形成されます。
スープやソースなど煮込む食品においては、長時間の加熱によって、特有の香り、風味が発現します。つまり、加熱により化学反応が加速し、香気成分や風味が増加します。みそやしょう油、パン、クッキー、焙煎コー ヒーなどの色や風味も、加熱や熟成過程で食品の成分同士の化学反応が起こり生成します。化学反応は高分子よりも低分子の成分の間で起こりやすくなります。 食品原材料に一般的に存在する低分子成分は甘味を呈す糖質、 たんぱく質から生じるアミノ酸やペプ チド類などです。した がって、食品を加熱すると最も起こり やすい反応であることから、温度を高くすることで反応を加速させます。
加熱は、消化を助けることにもつながります。吸水したお米を炊飯、魚や肉を火であぶる ことにより、高分子のでんぷんやたんぱく質が、未加熱の状態に比べ、分解されやすい構造に変化します。また、人の消化管で吸収されるためには、高分子をより小さな分子にする必要があり、 加熱は高分子のでんぷんやたんぱく質が消化酵素と接触しや すい構造に変化させます。
加熱は、寄生虫や微生物を死滅させる働きがある一方、発がん性の化合物が生成することもあります。家庭でも加熱により、微量ながら発がん性物質が生成しますが、がんになる程ではありません。しかし、表面のこげを意図的に食べることは避けたいところです。 欧米では、加熱した食品に発がん性のアクリルアミドが検出され、話題になりました。これは、ジャガイモに含まれるぶどう糖とアスパラギンというアミノ酸が、高温で加熱されて生じます。これは、加熱も度が過ぎると安全性を損なうことを意味しています。加熱のしすぎには、十分な注意が必要です。
まとめ
化学反応とは、反応物の結合が切れ、原子間に新しい結合が形成し、生成物が生じることです。化学反応では、生成物をつくるときに、結合を1度切らなければならないので、結合エネルギーの大きい分子などは、化学反応が起こりにくくなります。
化学反応を進行させるためには、化学結合を切るだけのエネルギーが必要になります。反応を進行させるためには、まずは反応物の粒子同士が衝突しなければなりません。しかし、反応物同士が衝突したからといって、必ず反応するとは限りません。多くの化学反応では、反応が起こるためには、ある一定以上のエネルギーを加えて、化学結合が切れやすい活性化状態にしなければなりません。加える最小のエネルギーを、一般的に活性化エネルギー(activation energy)といいます。反応物に活性化エネルギー以上のエネルギーを与え、反応速度を大きくするためには、反応物の濃度を大きくする、温度を上げる、触媒を加えることです。
スウェーデンの科学者アレニウスが提唱したアレニウスの式は、ある温度での化学反応の速度を予測する式です。反応速度は、10℃上がる毎に2倍になります。食品の賞味期限を設定するために、日本缶詰協会が設定する賞味期限策定根拠のひとつであるアレニウスの式に基づいた加熱加速度(虐待)試験を実施します。日本では、20℃を基準温度として、30℃で2倍、40℃で4倍、50℃で8倍の加速度で物質の反応が進むと考えて試験を行います。
多くの食品は、加熱処理により提供されます。この加熱工程において、食品中のたんぱく質の変性や食品原材料からの成分の溶出、メイラード反応をはじめとする化学反応など多くの反応が起こり、食品の呈味が形成されます。また、加熱は、消化を助けることにもつながります。さらに加熱は、寄生虫や微生物を死滅させる働きがある一方、発がん性の化合物が生成することもあります。